湖は表面に氷を張る不思議な自然現象
|
|
アルキメデスの浮力の原理
まず鉄の玉を水銀に浮かべてみます。水銀の比重は13.55、鉄の比重は7.87ですから、鉄の玉は水銀に浮きます。この時、鉄の玉が受けているアルキメデスの言う浮力はどれほどでしょうか。ちょっと面食らった人が居ましたでしょうか。そうです、浮いているのですから鉄の玉の重量と同じ浮力です。 では今度は水の中に、同じ鉄の玉を入れたら。これは沈んでしまいますね。この時、鉄の玉はどれほどの浮力を得ているでしょうか。 「沈んでいるから浮力はゼロじゃないの」 水銀→鉄の玉→浮く→水→沈む→浮力の順番で話を進めたのはいじわるでしたね。 水の中で沈んだ鉄の玉も、その鉄の玉の体積に等しい水の重量の浮力を得ているのです。 さて、今回は、その水自体の密度の話です。水は比重の元なので比重とは呼ばず密度と呼ぶのが一般的です。 水は温度により密度がかわります。その様子が図1にあります。 グラフは温度の変化による水の密度の変化です。温度が高くなると密度が低くなるのが解ります。つまり、同じ体積なら暖かいほうが軽くなるってことです。ダムにように水をせき止めた場合、冬になって温度が下がると水の体積は減って水面が下がることになります。 もっとも、水の体積が増えた結果ですから、100gの水をコップに入れて温度を上げても密度は下がりますが体積も増えますので同じ100gです。 図1のグラフを見ると水の密度が一番高いのは摂氏0度あたりでしょうか。このあたりを1度刻みで測定したデータで表したのが図2です。 どうも、4度あたりで一番密度が高く、0度あたりでは逆に密度が低くなっているのが解ります。理科年表を引くと3.98度が水が一番密度が高い温度となっています。 さて、簡単に「水の密度は4度近くで一番高い。つまり、同じ体積なら一番重い」とおぼえて、次に進みましょう。 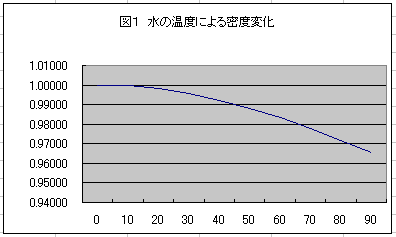
|
水が最も重いのは4度の時
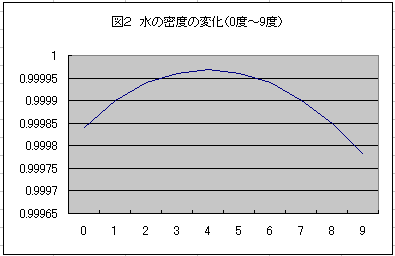 今年は暖冬で普段の冬ならば凍る湖が凍らなくて観光業が打撃を受けているってニュースが良く流れます。群馬県の榛名湖(はるなこ)が氷が張らないってニュースは何度も見ました。
湖が凍ると氷に穴を開けてワカサギ釣りとか、スケートとか、氷上ゴーカートが榛名湖(はるなこ)では楽しめるそうですが、今年は氷が張らなくて全て中止になったそうです。そのため冬の観光客を予定していた旅館や売店は商売にならないそうです。せめて半分でも氷が張ってくれればと思いますね。
今年は暖冬で普段の冬ならば凍る湖が凍らなくて観光業が打撃を受けているってニュースが良く流れます。群馬県の榛名湖(はるなこ)が氷が張らないってニュースは何度も見ました。
湖が凍ると氷に穴を開けてワカサギ釣りとか、スケートとか、氷上ゴーカートが榛名湖(はるなこ)では楽しめるそうですが、今年は氷が張らなくて全て中止になったそうです。そのため冬の観光客を予定していた旅館や売店は商売にならないそうです。せめて半分でも氷が張ってくれればと思いますね。あれ、湖は半分氷が張るってあるんだろうか。
冷蔵庫で製氷皿に水を入れて、完全に氷になる前に取り出すと中心が水のままの氷になりますよね。榛名湖(はるなこ)も回りから凍って、最後に湖の真ん中が凍るのでは。せめて回りだけでも凍ってくれたらと思うのですが、周辺すら氷が張らないようです。
さあ、湖が凍る仕組みを考えて見ましょう。たぶん、冷蔵庫の製氷皿とは違うのでしょう。
秋から冬になってきました。湖の上に吹く風は温度が低いので空気に接する水面が冷やされます。湖の水面より下はまだ暖かい状態です。
先のグラフを思い出して下さい。
水面で風によって冷やされた水は、下の水より温度が低くなりますから密度が高くなります。密度の低い下の水と交代して下に沈みます。変わって暖かい下の水が水面に出てきます。下に沈んだ水も周囲から温められて再度水面に出てくるかもしれません。
やがて、もっと気温が低くなって、湖全体が摂氏4度になりました。(正確には均一に摂氏4度にはなりませんが)まだ、冷たい風は水面を渡っていきます。もちろん気温は摂氏4度よりかなり低いです。湖の水面の水が摂氏3度になりました。下には摂氏4度の水が居ます。
摂氏4度の水は一番密度が高く、摂氏3度の水はこれより密度が低いので沈むことができません。沈めないってことはますます風に冷やされます。沈めないままどんどん冷やされて摂氏2度になっても摂氏1度になっても、下の摂氏4度の水よりは密度が低いので下に潜れません。
そして、下に沈まないまま、やがて水面は零度になって氷になります。
湖は水面から凍るのですね。やがて、氷を通して下の水も冷やされて氷が下へ下へと厚くなっていきます。
でも湖の魚達は氷に蓋はされますが、氷に閉じ込められることは無いのです。水の密度が一番高い摂氏4度の水の中を泳ぎ回れるのです。
もし、水の密度が摂氏0度で一番高かったらこうはなりません。
想像してみましょう。湖はどんどん冷やされて摂氏零度の水で満たされます。まだまだ寒い風は吹きます。すると、湖の水全体が凍ってしまいます。魚も氷に閉じ込められます。
こうなっては氷に穴をあけてワカサギ漁は出来ません。湖の底まで全部氷なんです。仮死状態で氷の中で生き続ける魚は良いですが、植物プランクトンなんかは凍って細胞膜が破壊されてしまうでしょう。すると、春になって氷が解けても魚は餌を取れません。折角氷が解けて動けるようになっても食べ物が無い状態になります。
水が摂氏4度で密度が最高になるって性質を持っているから、湖は魚の住める環境になったとも言えますし、大げさに言えば人類が誕生したことにも繋がるのです。
氷河期の時代でも氷の下で生物は生き続けることが出来たのです。最近の研究では5〜7億年程前に地球の全凍結があった後、生物の爆発的に進化が始まったって説もあります(そのうち書きますね)。
単なる偶然でしょうか、たった4度の違いで地球は生物誕生の揺りかごになったのです。不思議な水の性質を温度と密度の面から考えてみるとおもしろいですね。
北国でも不凍湖があるのは何故
ちなみに、気温が低い北国でも不凍湖とよばれる湖が存在します。北海道ではめったに氷結しない支笏湖(しこつこ)や摩周湖(ましゅうこ)です。
なのにはるか南の群馬県の榛名湖(はるなこ)は、何故氷結するのでしょうか。
これは、標高が高い(水面標高1084m)から気温が低いのに加えて、浅く広い湖(最大水深12.6m)だから水が冷えやすいのです。
水の全体量に比べて水面が広い浅い湖だと冷たい空気に触れる面積が大きくなるので冷えやすく、深い湖は水面の面積が少ないので凍りにくいのです。
また、浅い湖のほうが湖底の水が摂氏4度に短期間でなります。深い湖は摂氏4度の水が湖底に達するのに時間がかかります。その前に春が来てしまいます。
あの北緯50度のバイカル湖が不凍湖なのは、その深さに秘密があるのです。
 地球は1年に何回転するの?
地球は1年に何回転するの?
|
 アルキメデスの原理を実験で確認する
アルキメデスの原理を実験で確認する
|
|