熊本地震はどんな地震なのか(3)
|
|
地震発生から変化の状況
今回の熊本地震で亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに被災された多くの方へお見舞い申し上げます。直接支援の手を差し伸べられませんが、今回の地震の様子を情報でお伝えしたいと思います。本記事に利用した地表面の変動の図表は国土交通省・国土地理院の「最近の地殻変動情報」http://mekira.gsi.go.jp/project/f3/ja/index.htmlより引用・加工させていただいています。 国土地理院の「最近の地殻変動情報」は詳細の検定に時間がかかるために、データ収集後2週間ほど時間が遅れる。今回(6/14)入手出来るのは5月27日の測定結果を過去1年及び過去1ヶ月の変動として公表されている。 5月27日のデータによって、地震発生直後から直近1ヶ月の変化を読み取ることがdできる。 予震が起きたのが2016年4月14日21:26 MJ6.5 本震が起きたのが2016年4月16日01:25 MJ7.3 この間の、累積の地表面の移動は1年間データから、近々の状況は1ヶ月データから読み取ることができる。 また、被災地での一番の関心は相変わらず続く震度4程度の地震だろう。はたして熊本地震は終息に向かっているのかだろうを考えてみる。 近郊で起きている有感地震のエネルギー、つまり測定されるマグニチュードの日々の累積値の時系列変化で見ることができる。今回はまず地震の変化を見てみる。 |
本震後も頻繁に起きる地震
テレビでも時折「震度4」程度の地震が起きたとテロップが出ることがある。震度7に比べれは小さいが、日本全国で「震度4」の地震は月に1,2回有れば多い方で、その意味で熊本地震は終息の様子を見せていない。では、時系列変化はどうなのかを分析してみる。全国で起きた有感地震のデータは東日本大震災以降、ここにCSVの形式で掲載している。
この中から震源地名称の頭2文字が「熊本、天草、阿蘇、大分、有明」の地震を抽出する。これは今回の震源域を包括する地域になる。このデータから日々発生した地震のマグニチュードを集計していく。発生個数を集計しても小さな地震が多い場合と大きな地震が1回だけでは比較が出来ない。その日に地下で解放されたエネルギーの時系列変化をグラフ化してみる。実際にはマグニチュードは対数なので、1が二つと2が一つではエネルギー量が数倍違うのだけれど、傾向を読む程度で簡易的に加算してみる。
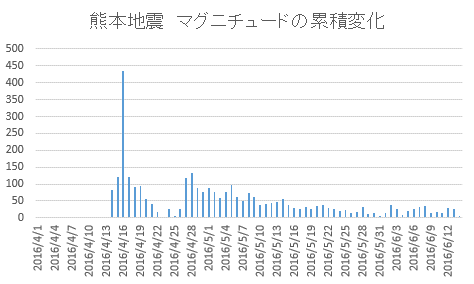 左端を見て貰うと4/1から予震の4月14日まで、この地域は地震がほとんど無い地域だったのが解る。14日の予震も大きなものだったが、16日の本震からは頻繁な余震で地下のエネルギーが解放されている。4月26日にはグラフは余震が治まったようにもも見える。ところが、4月27日の弱いピークが起きて、なだらかに累積マグニチュードは減少しているが、日々累積マグニチュードが20辺りで横ばいになっている(6月14日までの状況)。
左端を見て貰うと4/1から予震の4月14日まで、この地域は地震がほとんど無い地域だったのが解る。14日の予震も大きなものだったが、16日の本震からは頻繁な余震で地下のエネルギーが解放されている。4月26日にはグラフは余震が治まったようにもも見える。ところが、4月27日の弱いピークが起きて、なだらかに累積マグニチュードは減少しているが、日々累積マグニチュードが20辺りで横ばいになっている(6月14日までの状況)。残念ながら日々累積(一箇所では無くて広域で)が20。一回当たりマグニチュード3〜4(震度3〜4)程度の地震が今後も起きると予想される。
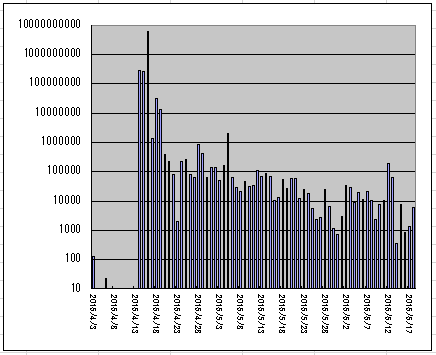 個数の集計だけでは無くて本当のエネルギー量をジュールに換算して計算してみたのがこのグラフなのだが、規模が違い過ぎるのでY軸は対数目盛にしている。一般的なグラフでは無いので読みにくいが、時系列的に規模が縮小していることが読み取れる。ただ、対数グラフを読むのは一般的統計手法では無いので、先の累積マグニチュードで十分と思う。
個数の集計だけでは無くて本当のエネルギー量をジュールに換算して計算してみたのがこのグラフなのだが、規模が違い過ぎるのでY軸は対数目盛にしている。一般的なグラフでは無いので読みにくいが、時系列的に規模が縮小していることが読み取れる。ただ、対数グラフを読むのは一般的統計手法では無いので、先の累積マグニチュードで十分と思う。
5月28日のGPS測定データ
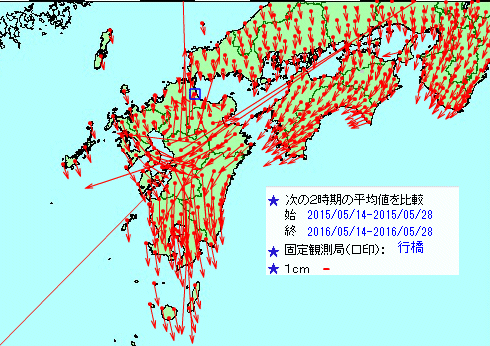 最新の5月28日のデータを見ると、あいかわらず東西へのすれ違い変化と南北への移動が読み取れる。これは1年前との比較なので地震後の累積変化と言える。
最新の5月28日のデータを見ると、あいかわらず東西へのすれ違い変化と南北への移動が読み取れる。これは1年前との比較なので地震後の累積変化と言える。熊本近辺では数メートル単位で地面が移動しており、その痕跡が地表面でも確認できる所が多数ある。垂直移動よりも水平移動が大きいので、段差として断層が検知される例は少ないようだ。
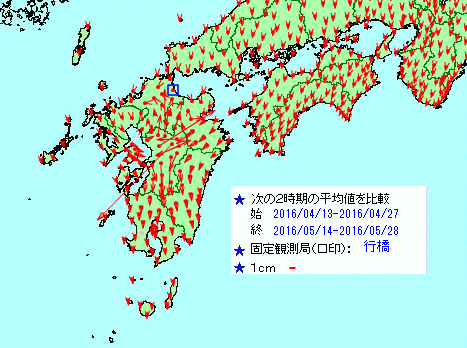 次の図は同じ5月28日のデータを1ヶ月前と比較したもの。一年と比べると変異の量が少ない。つまり、GPSデータによる地表面の動きはかなり治まっていると読み取れる。
次の図は同じ5月28日のデータを1ヶ月前と比較したもの。一年と比べると変異の量が少ない。つまり、GPSデータによる地表面の動きはかなり治まっていると読み取れる。正確には4月13日〜4月27日の平均と、5月14日〜5月28日の平均との比較だが、本震が起きた後であっても、急速に変化量が減少しているのが解る。
単に期間が短いだけでは無く、本震直後の地殻変動が治まりつつあるのか、長期的に継続するのかは来週のデータを見るとかなりはっきりするだろう。
5月28日の水平方向のデータ
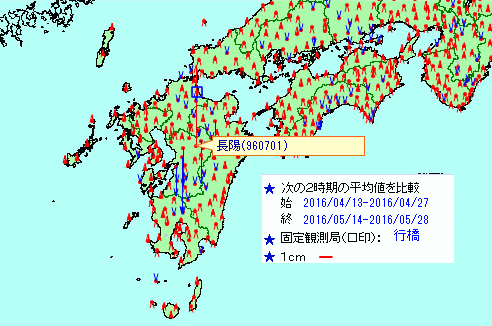 前回(2)で垂直方向の変化を「熊本を中心とした地帯が瀬戸内海に向かいながら周りの地盤に潜り込んでいる」と仮説を立てたが、今回のデータではその傾向は消えている。
前回(2)で垂直方向の変化を「熊本を中心とした地帯が瀬戸内海に向かいながら周りの地盤に潜り込んでいる」と仮説を立てたが、今回のデータではその傾向は消えている。全体的に沈み込んでおり、長陽のみが隆起している。
隆起するのは周りから押す力が加わっていると考えられるので、この周辺は市町村的には南阿蘇村の西側数kmの場所で、阿蘇山の西麓にあたる。
今回の熊本市周辺地盤が瀬戸内海へ向かうのを阿蘇山の手前の南阿曽村周辺が止めているだから、水平変化で上昇になってる)と考えられる。
大きな地震が起きているのに阿蘇山の噴火に変化が見られないのは、地下のマグマ溜りを変形させるほどの地殻変動が阿蘇山には起きていないのと、地下のマグマの量が活動の低迷期で少ないのが幸いしている。
問題は、熊本市周辺地盤の食い止めが進むのか、より東(阿蘇山)に進むのかで今後の災害の終焉か拡大かが決まるんだろう。
引き続き、GPSデータに着目しておきたい。
2016/06/15
Mint
Mint
